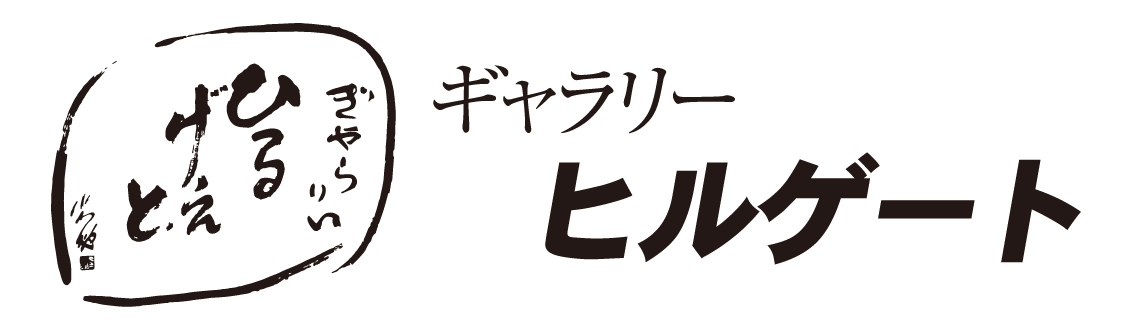野見山暁治 没後1年 追悼展 賛助出品:入江観・上葛明広・木村克朗・山口千里

基本情報
- 会期
2024年06月18日(火) 〜 2024年06月23日(日) - 会場
1階, 2階 - 時間
12:00~19:00(最終日~17:00)
野見山 暁治 ( NOMIYAMA Gyoji )
1920年福岡県生まれ。38年上京し、東京美術学校油画科予科に入学。本科2年生の頃から“池袋モンパルナス”と呼ばれたアトリエ村に暮らし、フォーヴィズムの絵画に傾倒する。当時の池袋モンパルナスには靉光・麻生三郎・赤松俊子(後の丸木俊)等、多くの画家が住んでいた。43年東京美術学校油画科卒業。応召の後病を患い、45年福岡の療養所で終戦を迎える。48年病気が治り、再び上京。自由美術家協会に出品、受賞し会員となる。この頃の自由美術には若く個性的な作家が集い、鶴岡政男、麻生三郎、難波田龍起、寺田政明等、池袋モンパルナスの住人だった先輩たちや山口薫等が芸術論を闘わせていた。50年最初の個展開催。この頃、郷里の福岡にしばしば戻り、筑豊の炭鉱風景を描く。52年渡仏。椎名其二、金山康喜、小川国夫らと親交を深める。58年安井賞受賞。64年帰国。無所属となる。68年東京藝術大学助教授(72年教授)に就任(81年辞職)。78年『四百字のデッサン』で日本エッセイスト・クラブ賞受賞。92年芸術選奨文部大臣賞受賞、94年福岡県文化賞受賞、96年毎日芸術賞受賞。2000年文化功労者顕彰。全国の戦没画学生の遺作を窪島誠一郎氏とともに収集、それらを展示保存する「無言館」(長野県上田市97年設立)にも尽力した。2014年文化勲章受章。著書『さあ絵を描こう』(河出書房新社)、『パリ・キュリィ病院』『絵そらごとノート』(筑摩書房)、『一本の線』(朝日新聞社)、『しま』(光村教育図書)、『署名のない風景』『うつろうかたち』(平凡社)、『アトリエ日記』『続アトリエ日記』(清流出版)画文集『目に見えるもの』(求龍堂)、『遠ざかる景色』(みすず書房)、『とこしえのお嬢さん』(平凡社)など多数。月刊誌「美術の窓」にて「アトリエ日記」を亡くなる直前まで連載。主な回顧展は83年の北九州市美術館、96年練馬区立美術館、2003年東京国立近代美術館、2011年石橋美術館・ブリヂストン美術館、2023年久留米市美術館等。
他、個展多数。2023年6月22日死去。享年102歳。
《賛助出品》
入江 観 (IRIE Kan)
1935 栃木県日光市生まれ。1957 東京藝術大学美術学部芸術学科卒業。1962 フランス政府給費留学生として渡仏。同国立高等美術学校にてモーリス・ブリアンション教室に学ぶ。1968 第7回国際形象展に招待出品(以後86年最終回まで毎年)1996 日本美術家連盟常任理事に就任。第14回宮本三郎記念賞受賞。受賞記念入江観展(日本橋三越本店)主催:美術文化振興協会、朝日新聞社。2000 女子美術大学名誉教授および女子美術大学付属高等学校・中学校校長となる。他、個展・グループ展 多数。
上葛 明広 (UEKUZU Akihiro)
1949 岐阜県飛騨市神岡町生まれ。1976 東京芸術大学大学院修了。1987~90 オーストリア・ウィーンに留学。2003~2015 女子美術大学美術研究科、女子美術大学芸術学部洋画教授。現在、野見山暁治財団理事長、女子美術大学名誉教授。他、個展・グループ展 多数。
掲載作品:「錫杖岳(北アルプス)」F10 油彩
木村 克朗 (KIMURA Katsurou)
1941 岡山県津山市生まれ。1967 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業(安宅賞・卒業制作買上げ)。1969 同大大学院修了、渡伊(ミラノ国立ブレラ美術学校~1975)。
すいどーばた美術学院主任、創形美術学校校長、京都芸術大学美術工芸学科学科長を歴任。現在、京都芸術大学客員教授。
他、個展・グループ展 多数。
山口 千里 (YAMAGUCHI Cenri)
福岡県生まれ。1976 聖心女子大学教育学科卒業。1991 国展出品、以後毎年出品。国展奨励賞。2013 風の芸術展市民大賞。個展(大阪髙島屋、日本橋髙島屋)他、グループ展 多数。現在、一般財団法人 野見山暁治財団事務長。
御挨拶
志半ばで戦没した仲間の画学生たちへの野見山先生の想いから始まった美術館「無言館」。その実現に協力し、館主として運営する窪島誠一郎さんを支援するため、野見山先生から託された作品の展示・販売を窪島さんから依頼されたのが、ヒルゲートでの第1回野見山暁治展でした。
私にとって野見山先生は、開館以来お世話になってきた丸木夫妻から「池袋モンパルナス」の隣人として聞いてきた「歴史上の人」であり、憧れの作家でしたから、この小さな画廊で個展を開かせていただくのは夢のような出来事でした。
やがて4年後の2011年に実現した第2回展は、「今度は来れた 野見山暁治展」と名付けて下さり、満員のお客様の前で楽しいトークもして下さいました。2021年、100歳の時に6度目の個展を開いて下さったのが生前最後となりましたが、その時には先生はとてもお元気で、何故か亡くならない人のように思ってしまっておりました。
1年目の御命日に際して小品による追悼展を開かせていただくことになり、身近におられた方々が賛助出品して下さることとなりました。いつも率直で自然体で、鋭いのに温かい先生のお人柄は、多くの人々を惹きつけてやまず、その作品は光を失うことなく輝きつづけています。
当展に展示できたのは小品ばかりですが、大作は全国の美術館に収蔵されましたので、これからも御高覧いただくことができます。肉体は亡くなられても、野見山先生は生きつづけていらっしゃるように思われます。
2024年6月18日 ギャラリーヒルゲート 人見ジュン子